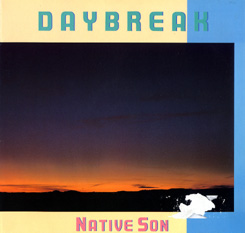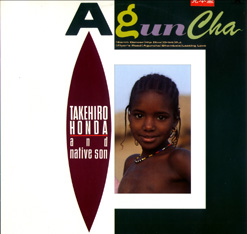〜ネイティブ・サンの活動(3):後期〜
ネイティブ・サンの歴史を長々と書いてきた本稿も、これが最後である。ここでは最後期のアルバム群『DAY BREAK』、『VEER』、『AGUNCHA』について述べてみる。 後期のネイティブ・サンの、最も大きな特徴といえるのは峰 厚介の不在だろう。峰 厚介は『DAY BREAK』を最後にバンドを退団する。 これにより、バンド名こそネイティブ・サンだが、完全に本田 竹広が100%音楽性を指揮するという「本田 竹広エレクトリック・バンド」へと変質してしまった。 実際、ラスト・アルバムの『AGUNCHA』には"TAKEHIRO HONDA&NATIVE SON"とバンド名がクレジットされている。つまり、TAKEHIRO HONDAとNATIVE SONは別物であり、ここに収められたサウンドは全てTAKEHIRO HONDAの音楽なのですよ、という意思表示とも受け取れる。 峰 厚介がバンドを退団したというのはネイティブ・サンの歴史上、最も大きな事件だったのは間違いない。 初期のネイティブ・サンが「ジャズのフィーリングが濃厚なフュージョンの時代」、中期が「試行錯誤を繰り返しながらバンドの安定期に入った時代」と呼ぶとしたら、後期のネイティブ・サンは「エレクトリック・サウンドを全面に出したポップ・ミュージックの時代」といえるかも知れない。 「本田 竹広エレクトリック・バンド」の奏でる音楽は、どの曲も歌詞を付けてヴォーカル・ヴァージョンにしてもおかしくない程、軽めでメロディアスなものが多い。 つまり後期の活動はネイティブ・サンのファンというより、純粋な本田 竹広ファンが聴くべき内容ともいえる。 なにせ曲は全て本田 竹広のオリジナルばかりだから、ファンには堪らないだろう。 ただし、この頃の本田 竹広は曲作りに相当苦しんでいたらしい。後年、本田さんに会ってネイティブ・サン時代の話をすると「あの頃はレコード会社との契約があったから、レコーディングのための曲作りが大変でねえ」と何度もしみじみと言っていたのを思い出す。普段、弱音をあまり吐かない本田さんが何度も言うのだから、相当なプレッシャーが掛かっていたのだろうと推察する。 先に述べたが、この頃になるとフュージョン・ブームも陰りを見せており、ネイティブ・サンを巡る状況も相当に変わってきた。また、さすがネイティブ・サンといえど息の長いバンドに避けられない、サウンド的なマンネリの感も呈し始めていたのも事実である。 先日、古いスイングジャーナルをめくっていたら、おもしろい記事に出くわした。 フュージョン・ブーム盛りの頃で「キミはネイティブ・サン派? それともザ・スクエア派?」という特集記事。今読むと思わず笑える記事なのだが、最後に「やっぱりキャリアの面から言えばネイティブ・サンが勝ち!」という文章で締めくくられている。この数年後、ネイティブ・サンは解散し、ザ・スクエアがバンド名を変えメンバー・チェンジを繰り返しながら、現在でも活動しているのを知っている今となっては、隔世の感がある。 ネイティブ・サン解散後、本田 竹広は実息・本田 珠也と一緒に"本田竹広&ビッグ・ファン"を結成。(本田さんに言わせれば、音楽的な内容はネイティブ・サンとそれ程違わないものだったという) その後、そうした流れは「アフリンバ」「ザ・ピュア」へと続いていった。 そしてもう一人、峰 厚介はネイティブ・サンを脱退した後は自身のバンド「峰 厚介クインテット」、さらに「峰 厚介カルテット」を結成して独自のジャズ世界を追及、遂に現在に至るまでフュージョンに手を染める事はなかった。 デビューから解散まで9年間に渡って活動してきたネイティブ・サンだが、この9年という活動期間は筆者に言わせれば「よく9年間も頑張りました」と、表彰状を送りたいとさえ思う。 実際、もともとネイティブ・サンはせいぜい3、4年くらいで終わるバンドだったのだ。バンドを作っては壊し、作っては壊しの根っからのジャズ・マン、あの本田 竹広や峰 厚介が10年近くも同じバンドをやっていたというのは、今から考えれば奇跡に近いようにも思える。 それが9年も続いたというのは、ひとえにバンドが商業的に成功したということ、そして青春をこのバンドと共に過ごした熱心なファンが最後まで付き添ったという事に尽きる・・・といえるかも知れない。 さて、前書きが長くなったが、ネイティブ・サン「後期」のアルバム群について書いてみよう。 まずは峰 厚介、最後の参加となる『DAY BREAK』。この作品、「中期」にするか「後期」に入れるか、かなり迷った。峰 厚介が参加している限り、このアルバムは当然「中期」に入れるべきだろう。しかし結局そうしなかったのは、この作品で展開しているサウンドは完全に100%、本田さんが主導権を握っている音楽だからだ。つまり、ここでは峰 厚介はあくまでサイドメン的な扱いであり、彼の音楽性がほとんど漂ってこないのが残念なところ。 少なくとも「初期」や「中期」にあった"本田 竹広と峰 厚介との音楽的な危うい拮抗"というものが、このアルバムでは感じられないのだ。だから敢えて、このアルバムを後期のトップに挙げてみた。 タイトル曲のスローな「DAY BREAK」は、さすが本田さんと言いたくなる「後期」を代表する曲で、このトラックのみネイティブ・サンの匂いがしっかりと残っている。峰 厚介のサックスが胸に沁みる。 しかしながら、その他の曲は打って変わってダンサンブル、かつ都会的サウンドで完全なポップ・ミュージック。すこ〜んと突き抜けた明るさがあるものの、ある意味で非ネイティブ・サン的なサウンド。初期のバンドを知っているリスナーにとっては、やはり軽過ぎるという印象を与えてしまう。 そしてこのアルバムから、リズム・セクションに米木 康志(ベース)、実息・本田 珠也(ドラムス)が参加となる。
さて次のアルバム『VEER』は、峰 厚介が抜けてバンドの痛い部分がモロに出た作品。 フロントのサックス担当は以前、峰 厚介から何度かサックスの手ほどきを受けた経験があるという藤原 幹典。何せ峰 厚介の後任なのだから、相当なプレッシャーがあった筈。ちょっと聴いていて痛々しい印象さえ受けてしまう。 藤原 幹典をめぐってはこんなエピソードがある。峰 厚介が抜けて後任のサックスを誰にするか、ネイティブ・サンのオーディションをやることになった。審査委員長はもちろん、本田 竹広。いろいろなサックス奏者をオーディションしたが、結局選ばれたのは藤原 幹典だった。 選ばれた理由は本田さん曰く、「お前は音がデカイから」。 いや嘘の話ではない。藤原さん御本人が、そう仰っているのだ。しかし、ただ「音がデカイ」という単純な理由だけで、栄えあるネイティブ・サンのサックス奏者に選ばれて良いのか? 良いのだ。こういう所がいかにも本田 竹広らしいのだ。 『VEER』はこれまでのフェンダーやクラビネットといった楽器よりも、シンセサイザーを多用した音作りで、前作『DAY BREAK』のポップ路線をさらに推し進めたものともいえる。曲によってはポップというよりディスコ調のものもあったりして、これがいかにも時代を感じさせる。もちろん初期のネイティブ・サンの匂いはまったくなく、この展開に戸惑ったファンも多かっただろう。 しかし、それがハービーのロック・イットのようにダンス・ミュージックにまで貶められていないのは、やはり本田 竹広の「ジャズ・ミュージシャンとしての最低限のプライド」のようなものが、あったからかも知れない。 それにしても正直にいって、ネイティブ・サンの全作品中、最も我が家のターンテーブルに載らなかったのがこのアルバムだ。 サウンドがどうこうしたの話ではない。もっと基本的、かつ重要なことでもある。そう、理由はひとつしかない。ネイティブ・サンのもう一人の主役、峰 厚介がここにはいないのだ。 峰 厚介が抜けたことで、これまでバンドが持っていたジャズのフィーリングがほとんどなくなってしまった。別に藤原 幹典のプレイが悪いわけではないのだが、彼と峰 厚介では音の佇まい、風格、そういったものの次元が違いすぎる。つまり峰 厚介はフュージョン・バンドにジャズの香りを持ち込み、それがバンドの魅力になっていたが、藤原 幹典はフュージョン・サックス・プレイヤーのままにフュージョンを演奏する、そのアプローチの違いというか。 峰 厚介以外のどんなサックス奏者が参加しても、あのネイティブ・サンのサウンドには成りえず、そしてネイティブ・サンは峰 厚介あってのバンドなのだということを、このアルバムは完全に証明しているように思う。 最後に紹介するのはネイティブ・サン名義でラスト・アルバムとなる『AGUNCHA』。 前作は個人的にちょっとがっかりだったが、この『AGUNCHA』は『VEER』よりは出来上がりが良い。峰 厚介がいないマイナス面はカバーしきれていないが、その代わり本田 竹広が最後の気力を振り絞って、良い楽曲を提供しているからだ。 晩年、本田 竹広が率いていた大所帯バンド、ピュアなどでも取り上げていた「オービット」も収録、そして「ラスティング・ラブ」は「DAY BREAK」と並ぶ「後期」の名曲バラード。 特にB面最後に収められた「ラスティング・ラブ」は「もうネイティブ・サンのアルバムはこれで聴けないのか」と思うと感慨もひとしお。 デビュー・アルバム『NATIVE SON』の一曲目「Bump Crusing」がネイティブ・サンのオープニング・ナンバーだったとしたら、この「ラスティング・ラブ」は文字通りネイティブ・サンのラスト・ナンバーだ。段々フェイド・アウトしていく音が余韻を残す。 『AGUNCHA』は、何度もいうようにネイティブ・サン最後のアルバムである。 しかし、ここには「ネイティブ・サン、さようなら」という感傷は、あまりない。 実際、ここに収められている音楽を聴いていると「ネイティブ・サンでは、音楽的に様々な事をやり尽くした!」という本田 竹広の悲鳴のようなものさえ感じてしまう。苦しい曲作りと、間髪置かずにやってくるレコ発ツアーから、これでやっと開放されるのだ。 メンバーにとっては、解散の悲しみよりも「このバンドで完全燃焼した」という満足感の方が、大きかったのではないだろうか。 峰 厚介が抜けた時点で「ネイティブ・サンは終わった」と一番痛切に思っていたのは、当の本田 竹広だったのかも知れない。 そして昔からの、ネイティブ・サンのファンも。 |
||||||